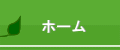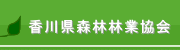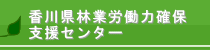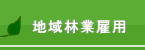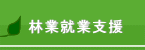年次有給休暇の請求権
年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。
年次有給休暇の請求権は、基準日に発生するものであるので、基準日から起算して2年間、すなわ
ち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅することになります。
 年次有給休暇の繰越しと時効による消滅 年次有給休暇の繰越しと時効による消滅
平成23年4月1日入社、平成23年10月1日年次有給休暇発生(出勤率8割以上の場合)
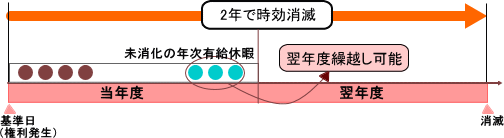
年次有給休暇を取得したことによる不利益な取扱いの禁止(第136条)
年次有給休暇を取得した労働者に対して、資金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、
欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。
年次有給休暇の賃金の支払い
年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、平均賃金
または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。
ただし、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による規定により、健康保険法の
標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の定めをしたときは、これを支払わなければなりません。
時間単位の年次有給休暇
労働基準法は、年次有給休暇の付与を原則として1日単位としています。
しかし、事業場で労使協定を締結することによって時間単位で年次有給休暇を取得することができます
(時間単位年休)。時間単位年休は、例えば通院、子どもの学校行事、官公署への諸届けなど必要な
時間分だけ取得できるため、多様なニーズに柔軟に対応することができます。
ただし、年次有給休暇の本来の趣旨を損なわないようにするため、時間単位年休は労働者の希望がある
ことが前提となっており、また、その上限は1年5日分までとされたいます。
なお、半日単位の年次有給休暇については、本来の1日単位での取得を阻害しない範囲で運用される
限り、労働者からの請求に応じて与えることができます。
 労使協定で定める事項 労使協定で定める事項
①時間単位年休の対象労働者の範囲
一部対象外とする場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られる。
②時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定める。
③時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定める。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げる。
④1時間以外の単位で与える場合の時間数
この場合は、2時間単位、4時間単位など
1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位で定める。
|
年次有給休暇の「継続勤務」の要件
継続勤務とは「在籍期間」を意味しています。したがって、必ずしも継続して「出勤」していな
ければならないものではなく、休職期間や長期病欠期間なども通算されます。
また、継続勤務かどうかは実態をみて判断され、例えば定年退職者を同じ会社で引き続き
嘱託社員等として再雇用する場合も、継続勤務しているものと取り扱われますので、勤務年数
を通算しなければなりません。また、定年退職時に退職金を支給している場合でも同様です。
ただし、定年退職後、再雇用までに相当の空白期間があり、客観的に労働関係が断絶して
いると認められる場合には通算されません。
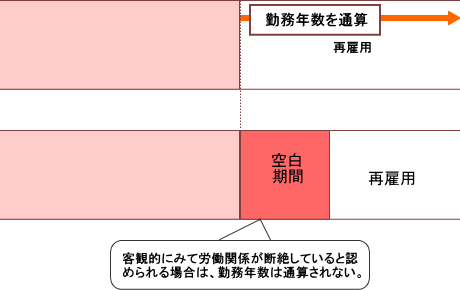
|