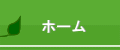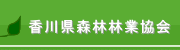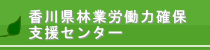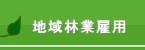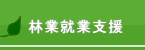|
|

|
改正労働基準法のポイント
施行期日 平成22年4月1日
労働時間の現状を見ると、週60時間以上労働する労働者の割合は全体で10.0%
特に30歳代の子育て世代の男性のうち週60時間以上労働する労働者の
割合は20.0%となっており、長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなって
います。(総務省「労働力調査」平成20年)
こうした働き方に対し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための
時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題と
なっています。
このため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の
調和がとれた社会を実現することを目的とした改正労働基準法が成立しました。
Ⅰ「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を
超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めること等とされます
時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものです。
労使の努力によってできるかぎり限度時間を超える時間外労働を抑制しましょう。
現行の取扱い
法定時間外労働を行わせるためには、①1日②1日を超え3か月以内の期間③1年間
のそれぞれについて、限度時間の範囲内で、延長することができる時間を労使(※)で
協定しなければなりません。(「36協定」)
②③の期間について限度時間を超えて働かせる場合は、時間数や手続等について、
労使で協定しなければなりません。(「特別条項付き36協定」)
※労働者側の協定当事者は、過半数組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
それがない場合は過半数代表者(事業場の労働者の過半数を代表する者)となります。
限定時間とは?
労働基準法で労働時間は1週40時間、1日8時間までと定められています。
労使で協定(「36協定」)を結んだ場合は、これを超えて働かせることが可能ですが
「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」において
一定の限度が定められています。(一部適用外あり)
限定時間を超えて働く場合とは?
臨時的に特別な事情ある場合に限り労使で「特別条項付き36協定」結ぶことで限度時間を
超えて働かせることが可能です。
| 期間 |
限定時間 |
限定時間(※) |
| 1週間 |
15時間 |
14時間 |
| 2週間 |
27時間 |
25時間 |
| 4週間 |
43時間 |
40時間 |
| 1か月 |
45時間 |
42時間 |
| 2か月 |
81時間 |
75時間 |
| 3か月 |
120時間 |
110時間 |
| 1年間 |
360時間 |
320時間 |
|
| ※1年単位の変形労働時間制をとっている場合 |
改正のポイント
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ
には新たに、
1 限定時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)
ごとに、割増賃金率を定めること
2 1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
3 そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
が必要になります。
(注)平成22年4月1日以降に協定を締結、更新する場合が対象です。
Ⅱ 法定割増賃金率の引上げ関係
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%
以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません
労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して
働くことができるよう、1か月に60時間を超える法定時間外労働について、
法定割増賃金率を5割以上に引上げます。
現行の取扱い
法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)
に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
改正のポイント
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
中小企業は適用が猶予されます。
※1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の
初日などにすることが考えられます。
深夜労働との関係
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた
場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上
となります。
法定休日労働との関係
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った
労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は
含まれます。
なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日と
それ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいものです。
法定休日とは?
使用者は1週間に1日または4週間に4回の休日を与えなければなりません。
これを「法定休日」といいます。
法定休日に労働させた場合は35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ
なりません。
引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を
付与する制度(代替休暇)を設けることができます
1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を
確保するため、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を
付与することができます。
改正のポイント
代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数
代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。
労使協定で定める事項
①代替休暇の時間数の具体的な算定法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
の4つがあります。
※この労使協定は事業場において代替休暇の制度を設けることを
可能にするものであり、個々の労働者に対して代替休暇の取得を
義務づけるものではありません。
個々の労働者が実際に代表休暇を取得するか否かは、労働者の
意思により決定されます。
代替休暇の時間数の具体的な算定方法
(例)次のような算定方法になります
代替休暇の単位
まとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会を確保する観点から
1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることとされています。
※半日については、原則は労働者の1日の所定労働時間の半分のことですが、
厳密に所定労働時間の2分の1とせずに、例えば午前の3時間半、午後の4時間半
をそれぞれ半日とすることも可能です。
その場合は、労使協定でその旨を定めておきましょう。
端数の時間がある場合
労使協定で、端数として出てきた時間数に、他の有給休暇を合わせて取得することを
認めていた場合は、代替休暇と他の有給休暇を合わせて半日または1日の単位として
与えることができます。
他の有給休暇には、事業場で任意に創設する有給休暇のほか、既存の休暇制度や
時間単位の年次有給休暇(※)が考えられます。(※この場合は、労働者の請求が前提です。)
| (例)1日の所定労働時間が8時間で、代休休暇の時間数が10時間ある場合 |
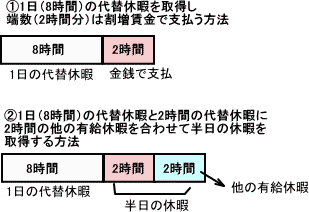 |
代替休暇を与えることができる期間
代替休暇は、特に長い時間外労働を行った労働者の休息の機会の確保が目的で
すので、一定の近接した期間内に与えられる必要があります。
法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内の期間で
与えることを定めてください。
※期間内に取得されなかっとしても、使用者の割増賃金支払義務はなくなりません。
当然のことながら、代替休暇として与える予定であった割増賃金分を含めたすべての
割増賃金額を支払う必要があります。
※期間が1か月を超える場合、1か月の代替休暇と2か月目の代替休暇を合算して取得
することも可能です。
(例)4月に6時間分、5月に2時間の代替休暇に相当する法定時間外労働を行った場合
※1日の所定労働時間が8時間代替休暇の取得期間を法定時間外労働を行った月の末日の翌日から2か月としている場合とする。 |
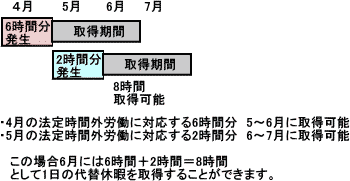 |
代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
賃金の支払額を早期に確定させ、トラブルを防止する観点から、労使で定めておく
べきものです。
取得日の決定方法(意向確認の手続)
例えば、月末から5日以内に使用者が労働者に代替休暇を取得するか否かを確認し、
取得の意向がある場合は取得日を決定するというように、取得日の決定方法について
協定しておきましょう。
ただし、取得するかどうかは法律上、労働者に委ねられています。これを強制してはなら
ないことはもちろん、代替休暇の取得日も労働者の意向を踏まえたものとしなければ
なりません。
割増賃金支払日
代替休暇を取得した場合には、その分の支払が不要となることから、いつ支払っておけば
よいのかが問題になります。労使協定ではどのように支払うかについても協定しておきましょう。
(例)賃金締切日が月末 支払日が翌月20日 代替休暇は2か月以内に取得
代替休暇をしなかった場合の割増賃金率50% 代替休暇を取得した場合の割増賃金率25%の事業場
|
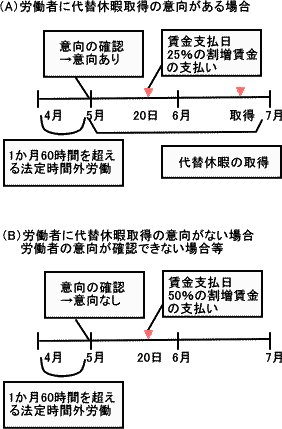 |
Ⅱ「法定割増賃金率の引上げ関係」については、中小企業には、当分の間、適用が
猶予されます
・中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の
数」で判断されます。
・事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
・法の施行3年経過後に改めて検討することとされています。
猶予される中小企業
| 業種 |
資本金の額または
出資の総額 |
または |
常時使用する
労働者数 |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
または |
50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
または |
100人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
または |
100人以下 |
| その他 |
3億円以下 |
または |
300人以下 |
|
| 業種分類は日本標準産業分類(第12回改定)に従っています |
(例)
製造業(「その他」の業種)
資本金1億円 労働者100人
→中小企業
資本金1億円 労働者500人
→中小企業
資本金5億円 労働者100人
→中小企業
資本金5億円 労働者500人
→中小企業 |
Ⅲ時間単位年休関係
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります
仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるよう
時間単位で年次有給休暇を付与できるようになります。
改正のポイント
過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を締結すれば、
年に5日を限度として、時間単位(※)で年次休有給休暇を与えることができます。
(時間単位年休)
※分単位など時間未満の単位は認められません。
※労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結さてていない
場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えられることが可能です。
今回の改正後も半日単位の年休については取扱いに変更はありません。
労使協定で定める事項
①時間単位年休の対象労働者の範囲
②時間単位年休の日数
③時間単位年休1日の時間数
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
①時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めます。仮に一部を対象外とする場合は、「事業の
正常な運営」を妨げる場合に限られます。取得目的によって対象範囲を定める
ことはできません。
②時間単位年休の日数
5日以内の範囲で定めます。
※前年度からの繰越がある場合は、当該繰越し分も含めて5日以内となります。
③時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間を基に定めます。
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
日によって所定労働時間が異なる場合
1年間における1日平均所定労働時間数(これが決まっていない場合は
これが決まっている時間における
1日平均所定労働時間数)を基に定めます。
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を記入します。
※ただし、1日の所定労働時間数を上回ることはできません。
時季変更権との関係
時間単位年休も年次有給休暇ですので、事業の正常な運営を妨げる場合は使用者に
よる時季変更権が認められます。
ただし、日単位での請求を時間単位に変えることや、時間単位での請求を日単位に
変えることはできません。
支払われる賃金額
時間単位年休1時間分の賃金額は、①平均賃金②所定労働時間労働した場合に
支払われる通常の賃金③標準報酬日額(労使協定が必要)のいずれかをその日の
所定労働時間数で割った額になります。
①~③のいずれかにするかは、日単位による取得の場合と同様にしてください。
|
|